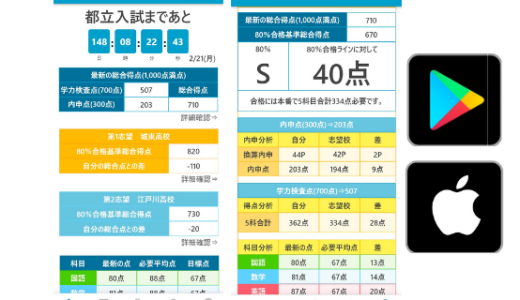植物、動物、細胞、遺伝、運動などについての単元です。
実験も多く印象に残りやすいため解ける人も多くいるようです。

都立理科の中でも特に実験と観察についての問題が出題される分野ですからね

実験の方法とか覚えるの苦手です…
なのでここでは実験の覚え方と、重要語句の勉強方法についてまとめました。
暗記系ではありますが、3年の最後まで重要になる単元なので早速勉強を始めましょう。

動画をアップしました
都立理科生物の傾向とポイント
すべてが4択の記号選択問題の全4問で、配点16点の問題です。
年度によって問題数が前後する可能性があるので注意してください。

特に植物の問題が出題される可能性が高いです

動物に関する問題だと消化やでんぷん分解の実験がたくさんでますね!
大問2⃣と似ており、実験の結果やその正しい理由の組み合わせ問題が主体です。
実験の方法や計算、水溶液の役割などが頻出するので必ず覚えましょう。
都立生物の解き方のコツ
選択肢を半分にする方法はすでにこちらに書いてあります。
 都立理科大問1⃣小問集合のコツ
都立理科大問1⃣小問集合のコツ
特に溶液の性質やその実験のする理由を選ぶことが多いので、セットで覚えておきましょう。
実験の説明はとても重要
実験についての問題がでますが、その実験の前提条件が読み取れないと問題が解けません。
例えば遺伝の問題では顕性(優性)遺伝子と潜性(劣性)遺伝子の計算をします。
その時に組み合わせる個体の条件が把握できていないと答えを間違えます。

選択肢の中に間違った場合の数字も書かれているので引っ掛かりがちな問題ですね
必ず説明文中の条件には線を引きながら確認していきましょう。
【重要】都立理科の傾向の変化
「①の比較から、デンプンは2の働きによって~」と③まで続き、①②③それぞれに入る言葉を選択肢から選ぶ問題です。
内容は完全に基礎問題です。
そして実験の結果だけではなくなぜその実験をするのか、その過程の理由について学んでおけば大丈夫です。
都立入試生物の勉強方法
生物の勉強は実験をする内容から優先的に覚えます。
出題される傾向として実験結果についての考察と理由が問題になるからです。

特に絵によって解説されているところはノートに書きまとめましょう

教科書の挿絵がそのままに問題がでてくるからですね!
その他の必要事項は以下の通りです。
①生物の重要語句
【植物】
⇒核、細胞膜:植物と動物の細胞に共通しているつくり
⇒細胞壁、葉緑体:植物の細胞のみにあるつくり
⇒維管束:水と養分を運ぶ道管と葉で作った栄養分を運ぶ師管の束
⇒光合成:光を受けて二酸化炭素と水を酸素とでんぷんをつくる働き
⇒呼吸:光合成と全く逆の反応。
【消化と吸収】
⇒炭水化物:だ液、すい液でブドウ糖に分解される
⇒タンパク質:胃液やすい液でアミノ酸に分解される
⇒脂肪の消化:胆汁、すい液で脂肪酸とモノグリセリドに分解される
⇒組織液:血しょうが毛細血管から染み出したもの
⇒肝臓のはたらき:アンモニアを尿素に分解する
【感覚と運動】
⇒神経系:脳と脊髄の中枢神経と、感覚や運動などの末梢神経
⇒刺激と命令:感覚器官⇒感覚神経⇒せきずい⇒脳⇒逆走⇒運動神経
⇒反射:感覚器官⇒感覚神経⇒せきずい⇒運動神経
②植物の勉強優先
前述したとおり、動物よりも植物の方が出題頻度が高いです。

動物単元よりも植物単元の勉強を優先しましょう
一年の初めから、植物の分類から覚えてください。
まとめ
例年生物は受験者の得点率が50%以上あります。
みんな半分以上正解するのですね。
正解できないとそれだけで他の受験生に差をつけられてしまいます。
今すぐ復習するためにノートをまとめて、勉強し始めましょう。